
伊都国の平原古墳は卑弥呼の墓と考えられる理由
こんにちは!yurinです。糸島市は、古く半島部は「志麻(しま)郡」、内陸部は「怡土(いと)郡」でした。天照大神をお祭りする伊勢志摩地方を想起…

こんにちは!yurinです。糸島市は、古く半島部は「志麻(しま)郡」、内陸部は「怡土(いと)郡」でした。天照大神をお祭りする伊勢志摩地方を想起…

こんにちは!yurinです。今日は、神武天皇の活躍年代はいつ頃なのか?考えてみます。神武天皇の活躍年代は3世紀末『日本書紀』の年代を、その…

こんにちは!yurinです。このたび新元号「令和」が公表されました。とても美しく気品がある元号です。『万葉集』からの典拠ということで、日本の古…

こんにちは。Kaoriです。9月に秋の古代史遠足「多摩川沿いの古墳と神社を歩く旅」を開催しました。(秋の企画ですが投稿が12月になってしまいま…

こんにちは、オオクです。埼玉県の寄居町(よりいまち)にヤマトタケルにまつわる伝承があります。寄居町は、埼玉県の北西部、荒川の清流が秩父の山間か…
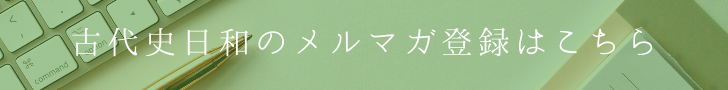
こんにちは。Kaoriです。2015年にひっそりと産声を上げた「古代史日和」が、この度、記念すべき10周年を迎えることができました!これもひと…

こんにちは!Kaoriです。先日、石川県七尾市にある須曽蝦夷穴古墳を訪れました。 須曽蝦夷穴古墳(すそえぞあなこふん)と読みます。目的地に向か…

こんにちは。Kaoriです。先日、春の古代史遠足「縄文の村と武蔵国府跡を巡るツアー」を開催しました。※企画のネーミングは終わってから変更しまし…

こんにちは。Kaoriです。2024年の8月で、古代史日和の活動も10年目に入ったこともあり、PHOTO企画を開催しました。題して「古代史 P…

明けましておめでとうございます。Kaoriです。2022年もどうぞよろしくお願いいたします。2021年も古代史日和でPHOTO企画を開催しました。…


こんにちは!Kaoriです。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。古代史日和でPHOTO企画を開催しました。題して「古代史 PHOTO Aw…

こんにちは!オオクです。▼関連記事6世紀古墳で東日本最大級の七輿山(ななこしやま)古墳武蔵国造の乱の後、現在の群馬県藤岡市にあたる緑野(み…

こんにちは!オオクです。今回は、群馬県藤岡市で今注目の古墳、伝説や規格なども興味深い七輿山(ななこしやま)古墳について紹介します。…

こんにちは!しむちゃんナウです。縄文時代の土偶一族の時期別、地域別の広がりをお話しします。草創期早期前…